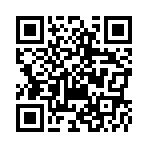2009年08月31日
涸沢か奥多摩か 10月第1週の悩み

(C)Yama-Kei Publishers Co., Ltd.,
知人が関わっている山イベントが9月4日から涸沢で開催される。『涸沢フェスティバル2009』というもので、近頃急速に耳にするようになった山ガールというキーワードが、まさにぴったりのイベント。
いつも泥だらけ汗臭い格好で山や沢をごそごそ這い回っているボクには、このイベントに集うオシャレな方々がとてもまぶしく見える。
そういえば、かつて山を始めたばかりの少年時代に目にした、アメリカのBack Packing Magazineに登場するジャンスポーツやケルティのフレームパックを背にしたアメリカンなファッションのバックパッカーや、ヨセミテに集う長髪クライマーの姿もとても新鮮に見えた。パタゴニアを創立したシュイナード氏もまだ若く、かなりイカシてた。
高校生のボクにとって、それはとても『カッコイイ』ことだった
つづきはこちらClubNature+へ
2009年07月23日
岩尾根の悦楽
クリックで拡大 (c)harry
奥穂から西穂(西穂~奥穂)へと向かう岩尾根は“難しいルート”と一言で表現されてしまっているけれど、それは“困難なルート”という難易度の高さではなく、危険度の高さ。アルパインと比較すればルート的にはどうということのないものだけれど、危険度はかなり高い。
たとえば奥穂からジャンダルム手前の馬の背を越えた先の下る部分。空中に飛び出しそうなプチ・アルパイン感覚が味わえる場所だ。奥穂高岳から歩くと、ここが一番怖さを感じる。これは難易度の問題ではなく、高度による精神的な問題。けっこうドキッとさせられる。ガスっていて周囲が見えないと、どうということなく通過できる場所でもある。ここで動きが硬直してミスすれば、そのまま墜落してしまう。多くの場合、ここが渋滞している。
つづきはこちらClubNature+へ
2009年07月17日
憧れの屋久島
クリックで拡大
ハリー氏撮影・提供 (C)Harry
20代半ばを過ぎた頃、偶然にも立ち寄った大きな八重洲ブックセンターの写真集コーナーで、これまた偶然に手にした写真集があった。
当時付き合っていた女性は現在のJR東日本企画という広告代理店の前身にあたる弘済広告社の人で、黒木瞳を華奢に可憐に、そして涼やかな目元を付加させたような、ものすごく魅力的な人だった。競争率もそれなりに高かったと思う。
コンラート・ローレンツだとかソローだとか、そういったClubNatureのコンセプトにもしている数々の偉大なるネイチャー的先駆者を教えてくれたのは彼女だったし、ボクがカヌーを始めたきっかけも、実は彼女だった。
Mさんと二人で入った八重洲ブックセンターで最初に彼女が興味を示し、そして気づいたらボクが買って所有していた写真集は尾白明夫さんによる『屋久島』だった。朝晩、とにかく気づけば四六時中これを眺めていたし、眺めれば眺めるほど新しい発見と驚きがあった。
つづきはこちらClubNature+へ
2009年07月01日
ダラリ系で楽園キャンプ

クリックで拡大 (C)マッツン
ピシッ、バシッと張るのもいいけれど、どことなく力の抜けたこの張り具合、さいこ~です。かっこいい。リキみがない。がんばってるゾ感がない。つまり、ほどよい自然体。
見れば見るほど・・・ほんとうに気持ちよさが伝わってくるオシュマンズの広告用写真。カメラマン、ディレクター・・・良~くそこのところをわかってますね。ファションで言うところの着崩しテクニックのようなものか。
山岳ではこうもいかないから、これはあくまでもキャンプでの遊び心か。
こんなイメージをイラストにしてくれたのは、お馴染みのイラストレーター「マッツン」。
続きはこちらClubNature+へ
2009年06月17日
オールドクライマー

クリックで拡大
1972年5月に発行されたCLIMBING誌の表紙を飾るのは、ひとりの年老いたクライマー。幾多の困難に立ち向かったことを予感させる厳しい眼差しと、不屈の気持ちが見て取れるその口元。
ちまたに溢れる好々爺のように全てを達観したかのような穏やかさとか、諦めとか。そんなふにゃふにゃしたオーラなどこの老人は微塵も感じさせない。かっこいいではないか。この、たった一枚の古びた雑誌の表紙写真に、現在の、老人が堂々と胸を張って、人生で積み上げてきた強さや気概、気迫を示しにくい社会というものに気づかされてしまった。
さて、着古したウールの着衣からのぞく、まるで手袋のように見えるごっつい手には、まるでスイス名匠・ベントにも見えるピッケルがのっている。
ベントは、かのエドモンド・ヒラリー卿とテンジン・ノルゲイが、1953年のエヴェレスト初登頂を成し遂げたまさにその時、天空に掲げたピッケルだ。この当時のピッケルのピック(刃先)は、写真のように真っ直ぐに伸びている。
それは、ウォルター・ウェストンが愛用していたスイスのエルクにしろ、フプアウフやシルトなども同様だ。エルクはヘッドとシャフトの部分のデザインが特徴的なので
続きはこちらClubNature+へ
2009年06月12日
アウトドアで音楽ダス・ダンスダス

(C)マッツン
このイラストは友人であるイラストレーター兼グラフィックデザイナー“マッツン”の作品。
これを眺めていると、波間遠くから陽気にシャウトする音楽が聞こえて来る。ゲーンズブールの官能とウェット・ウィリ-のソウルフルなかっこよさ、あるいはボズ・スキャグスの限りなくサザンロックっぽい匂いも漂ってくる。
とにかく、理屈抜きにカッコイイのだ。こういうイラストが描ける奴やグッとくるような音楽を作れる奴が、ほんとうに羨ましい。
キャンプに行って騒々しさに巻き込まれるのはゴメンだけれど、音楽をライブで、それも大自然の中で堪能できるのは天国だ。アーティストがステージに姿を現し歓声が沸き起こった次の一瞬、ふと生じた無音のエアポケットに風のざわめきが流れ、それを埋めるかのように音楽が始まる鳥肌感がたまらない。
続きはこちらClubNature+へ
2009年04月30日
大好きな場所 美ヶ原・霧が峰

毎年今頃の時期になると、もう胸騒ぎがしてたまらない。
八ヶ岳や谷川岳、日本アルプスの山々は、まだ深き雪の下にその巨体を埋もれさせているけれど、雪崩が頻発し、夏日が増すごとに着衣を脱ぐように黒い岩肌が露出する。冬の間、岩の割れ目で凍結膨張していた氷が溶けるので、初夏は落石が多くなる。
いまの時期の春山は、もちろん冬山の装備が必要だけれど、それでも冬に較べたら気持ちよさは格別で、真っ青に晴れ渡った空に真っ白な鋒々が突き上げ、そこにアイゼンとピッケルを突き立てて登る気分は言葉にしようがない。
当初は奥さんに岩登りや冬山技術をレクチャーしていっしょに登ろうという目標があったのだけれど、何度かクライミングそして冬の八ヶ岳・阿弥陀岳南稜そして春の白馬主稜などを登り、数回ほど怖い思いをしただけだったのだけれど“もう行きたくない”と見向きもしなくなってしまった。つまり、これがキャンプをするようになったきっかけのひとつ。
現在、山は山岳会と山岳部のOB山の会のみ。ハイキングのほか奥さんを連れて登ることはなくなってしまった。キャンプをするようになった最近では家族連れで、少しでもこうした気分を味わうために、冬から春にかけて必ず訪れる場所がある。それが美ヶ原・霧ヶ峰。
続きはこちらClubNature+へ
2009年04月23日
ディア マイフレンド
 昨日の午後、友人が遊びに訪れた。ボクは彼のことをマッツンと呼んでいて、かれこれ20年以上の付き合いになる。ボクは知り合いこそ多いのだけれど、友と呼べる存在はとても少なく、数人しかいない。そんなボクにとって数少ない大切な友がマッツン。
昨日の午後、友人が遊びに訪れた。ボクは彼のことをマッツンと呼んでいて、かれこれ20年以上の付き合いになる。ボクは知り合いこそ多いのだけれど、友と呼べる存在はとても少なく、数人しかいない。そんなボクにとって数少ない大切な友がマッツン。彼と出合ったのはずいぶん昔のこと、裏原宿にあったデザイン事務所。青山のモッズヘアーなど、当時としては憧れの対象だった綺羅星のようなクライアントの数々。建築デザインからグラフィック・広告制作まで手がけるデザイン事務所で、ここでマッツンと出会って以来の長い付き合いだ。
彼の魅力はデザインもさることながら、原初的なパワーがみなぎるイラストにある。まさにアートだ。このアートにぜひコピーをコラボしてみたい。マッツンの壁画を制作している噂は自然と耳に入ってきていたため、チャンスがあれば・・・と、そう常々思っていた矢先、面白い案件が入ってきた・・・
続きはこちらClubNature+へ
2009年03月20日
春と冬とが交錯する猪苗代の風景
Inawashiro lake
これは2月下旬の猪苗代湖の風景。
あちこちに出かけはするのだけれど、撮った写真画像は撮り散らかしたまま、ほとんど整理などせず消去したり、CDに焼いたり。今日は日曜締め切りの原稿を先ほどメールで送信したため、ほっと一息。久々の余裕ある時間が持てたため、PC内の画像を捨てていたら、これが出てきた。
福島にスノーハイクしに行った時に、意外にも凍結していない猪苗代湖を前にして、ちょっとシャッターを切った、ただそれだけの写真のはずだった。
風というものは目に見えない。対象物があってはじめて風の存在が知れる。古には吹流しとか旗とか、神が宿るとされたのはこうした所以によるものなのか。ともあれ、このとき横殴りの、立っていられないほどの風が吹き荒れていて、湖もさざ波立っている。これだけ見れば、桜前線も北上し始める今頃の時期の風景に見える。
まあ失敗のような写真だけれど、春に侵蝕される冬があるように思った。イルカじゃないけど、名残(なごり)冬。去り行く冬の香が、実に名残惜しい。考えると、ボクの人生はあれもしたいこれもしたい・・・と心残りで名残惜しむことばかり。
カメラは富士フイルムのシルヴィ。F2.8、24㎜の広角で明るいレンズのフィルムカメラだ。これにポジフィルムのベルビアで撮影してみた。画像加工、補正は無し。
本館はこちらClubNature+へ
2009年03月16日
清流に祝福された夢のトレイルの大好きな山小屋

夏へと馳せる思い
登山をしていれば、きっと誰にでも心に残る山小屋というものが存在するだろうと思う。ボクの場合どうも信州に集中していて、その理由を尋ねると少年時代の春休み夏休み冬休みを信州の山々を登って過ごしていたからだとわかった。
もちろん今までに北アルプス以外の山域に出かけているけれど、中学高校の少年時代に情熱を傾けた山々というものは、それ以降のものと較べると別格にも思える。そういえばマクドナルドなどが幼少時期の子供らにターゲットを絞るマーケティングをしているけれど、あれは幼少期に味わった味覚は生涯の嗜好をコントロールする、ということかららしい。であれば、幼少期に近い少年時代に経験した物事というものは、その後の趣味志向を左右してしまうのかもしれない。
まあ、そんな話はさておいて。たとえばボクにとってマーラーの交響曲第五番の第四楽章アダージョは涙が出るほど美しい旋律で、もうこれ以上のものは存在しないだろうというほどの存在なのだけれど、その山小屋を脳裏に思い描いた際に、このアダージョが鳴り響くかどうか、というのがボクの目安だ。
本館はこちらClubNature+へ
2009年02月03日
美しき日本の山々へ Esquireとの偶然の出会い

クリックで拡大
ぶらりと入った古書店の店頭には数々の雑誌が山積みされていた。その中に「山と渓谷」とか「岳人」とか山岳雑誌のバックナンバーが無造作に積まれ、それを丹念に眺めていると・・・なんと下のほうから「岩と雪」なんていう、今は無き、かつて愛読していた雑誌まで発見できた。
さて帰ろうか、と思いかけたとき。チラと視線の隅に見えたのが見慣れた風景と、そこにでかでかと印刷された“山々へ”という文字。ボクは考える間もなく、思わず体が反応してしまい、気づけば雑誌を手にしてした。雑誌はEsquire(エスクァイア)。2008年12月号で「美しき日本の山々へ」という特集号だった。
表紙を飾っているのはタレントの加瀬亮さん。北穂へのルートで撮影されたと思われる、気持ちよさそうなスナップだった。
ページをパラパラとめくると、一枚の写真に目は釘付けになった。それは、今まで何度かお世話になったことのある、見慣れた北穂小屋のサロン。それも、ボクの大好きな席でくつろぐ加瀬さんの姿だった。使い込まれテロテロと黒光りする調度品は貫禄・・・
続きは引越し先ClubNature+へ
2008年12月10日
白馬・八方尾根上のカマボコテントと不帰(かえらず)の嶮
 山仲間との冬の楽しみのひとつが、八方尾根で行われる冬山・スキー合宿。合宿とは言っても訓練はごく一部で、そのほとんどは自由山行として五竜だとか不帰キレット方面を楽しんだり、あるいは八方尾根の唐松岳寄りにある丸山ケルンまで登って、そこからアイスバーンの稜線をスキー滑降して楽しんだり。
山仲間との冬の楽しみのひとつが、八方尾根で行われる冬山・スキー合宿。合宿とは言っても訓練はごく一部で、そのほとんどは自由山行として五竜だとか不帰キレット方面を楽しんだり、あるいは八方尾根の唐松岳寄りにある丸山ケルンまで登って、そこからアイスバーンの稜線をスキー滑降して楽しんだり。ボクの場合、もっぱらスキー。スキーをザックにくくりつけ、唐松岳直下にスキーをデポしてピストン(往復)し、デポしておいたスキーのかたわらでお茶で暖まったらカリカリに凍てついたつるつるの稜線を、眼下に360度のパノラマを眺めながらビューんとスキー。ボクの大好きなスキーコースの一部がこの写真。真正面に見えているのは不帰の嶮(不帰キレット)。かえらず、と読む通り、なかなかの難所でアドレナリンも出るルート・・・・
続きはこちらへ(Blog引越し中)
2008年06月13日
定年後のアウトドア

江戸時代の本草集を眺めていて思い出しました。以前、戸隠イースタンでキャンプしたときのこと。戸隠山に登るため夜明けとともに起きだして、準備運動をかね付近を散策していると、お隣の戸隠キャンプ場で、チェアの前の三脚で何かを狙っている人影が見えました。撮影かな、と思って近づいてみると、カメラと思えたものは大きな単眼の望遠鏡でした。
年のころ60代後半あるいは70を越えているかもしれません。望遠鏡を覗いては、下を見て、また覗いては、下を・・・「いったい何をしているのだろう」と思い横に移動。視角の前景にあったテーブルの陰では、足を組み、その上でスケッチブックに何やら描いている様子。遠目に見ていると、気配を悟られたのか、彼はこちらを振り向いてニコリと笑顔。思わず「おはようございます」と僕もペコリ。これがご縁で、ずうずうしくもお茶をご馳走になり、ついでにスケッチの中身も鑑賞させてくれました。

そこには色鉛筆の繊細なタッチで数々の野鳥が描かれたいました。まるで江戸の本草集を眺めているような気分です。テーブルの上には、ものすごく大きなケースに、同じくものすごい色数の色鉛筆。どうやら外国製のようでした。その方の「定年後にキャンプしながら鳥のスケッチを始めました。楽しいですよ」という言葉に触発されて、僕も安いオペラグラスを片手にスケッチを始めました。調べてみると、戸隠キャンプ場はバードウォッチングのメッカでした。さて、僕の作品は・・・稚拙でまだまだお見せできるレベルではありません。そのうち、記事にアップしようとは思っていますけれど(^^;;
 さてアウトドア用の双眼鏡を持っている方もよく見かけますが、コールマンの名を冠したこんな双眼鏡もあります。コールマンとオリンパスのコラボレーションで生まれた「Coleman Binoculars 8×21」です。倍率は8倍、対物レンズ有効径は21ミリ。これの優れている点は170gという軽量・コンパクトさは当然のこととして、眼鏡をかけていても使用できる、という点です。目当てリングを折り返せば、眼鏡をかけたまま普通に使用できます。コールマンの名を持つオリンパス製品です。キャンプの際に首からぶら下げていても様になるアイテムです。
さてアウトドア用の双眼鏡を持っている方もよく見かけますが、コールマンの名を冠したこんな双眼鏡もあります。コールマンとオリンパスのコラボレーションで生まれた「Coleman Binoculars 8×21」です。倍率は8倍、対物レンズ有効径は21ミリ。これの優れている点は170gという軽量・コンパクトさは当然のこととして、眼鏡をかけていても使用できる、という点です。目当てリングを折り返せば、眼鏡をかけたまま普通に使用できます。コールマンの名を持つオリンパス製品です。キャンプの際に首からぶら下げていても様になるアイテムです。
ClubNatureメインはこちら
2008年05月30日
ヴァレンジヴィユの崖の小屋

季節は初夏なのでしょうか。さわやかな海風が止むと、むんとした暑気が、旺盛な緑の中から昇りたつようです。
じっと眺めていると、木に覆われた中から小屋に続く想像の小路が浮かび上がってきて、そこには、やや湿り気を帯びた空気の、湿った土と緑の青くさい匂いがただよっています。
これはクロード・モネが好んで訪れたヴァレンジヴィユの丘。遠くに見えるのはヨットあるいはディンギー? 時刻は正午少し前。左にある日は、やがて右手の水平線に沈むのでしょう。
暖炉があって、二階建て。この小屋からは、ドラマチックな日没が見えるはずです。そして冬になれば。小屋の外では、海がびょうびょうと青みがかった灰色の風に包まれて。そんな音を聞きながら、秋に作っておいた魚の燻製をローストする暖炉の炎は、とても幸せです。
いつかは、こんな家に住んで、のんびり釣りを楽しんでみたいものです。
ClubNatureメインはこちら
2008年05月22日
ジヴェルニーの春

この絵はクロード・モネが1880年に、ジベルニーの借家の春を描いた作品です。春の柔らかな日差しが揺れる夢のような光景ですが、なぜかこれを眺めていると、とても寂しくて悲しい気持ちになってしまいます。
セーヌ川そばの田園、ジルベニー。庭に植えられているのは果たして野菜なのか、ハーブなのか。肥沃な土が植物を旺盛に育てています。乾いた土とそこに混じるように堆肥が香ってくるようです。
静かな午後。耳を澄ませば蜂の羽音がせわしげに聞こえてきます。足元を見れば、乾いた赤土のでこぼこをアリたちが動き回っています。こんな中、小さなタープの下にバイヤーを持ち出して、フローズンダイキュリでも飲みながら読書したらさぞ気分がいいでしょうね。
ClubNatureメインはこちら