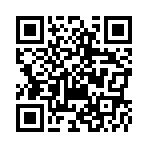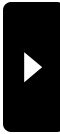2016年09月20日
黒部源流・赤木沢 北アで一番美しい渓

埋蔵金伝説のある折立の登山口からおよそ4時間。
ブナの森の中の九十九折れの急登に汗を滴らせながら至ったのは、雄大な北ノ俣岳や黒部五郎など黒部源流の山々の前に建つ太郎平小屋だった。
ここから薬師岳の裾野にある薬師峠のテント場にテントをデポしてピストン。テントやシュラフ、コッヘル、酒、食料、着替えなどが無くなり、軽くなったザックを背に太郎平小屋から黒部の源流に向けて、ようやく薬師沢に沿って登山道を下ることになる。

続きはClubNatureブログへ
2014年09月18日
白い岩に碧い水の美渓 丹沢・小川谷廊下
やっぱり夏は沢登りにつきる。
うだるような夏の一日、白いゴルジュにキラキラ飛沫をあげる碧い水と、戯れ遊ぶ。
あ~、なんて贅沢なんだろう。
梅雨が明けて2週間目。前の記事の繰り返しになってしまうけれど、山用語で梅雨明け後の2週間は天気が安定することから「梅雨明け十日」と呼ぶ。このときの週末は天気の安定期間最後の土・日だった。
黒部の源流を稜線まで詰めあがり、三俣の山小屋で一夜を過ごせたなら、きっと幸せだろうな・・・なんてことを想像するものの、自由になるのは土曜日のみ。夏の山の香りがぷんぷんするマーラーの5番を聴きながら、あれこれ考えた結果、決めたのは西丹沢の玄倉川・小川谷廊下。
石灰岩が多い丹沢にあって、白い花崗岩のゴルジュに碧き清流が流れる丹沢一の美渓。唯一懸念されることは、あまりにも美しすぎるために多くの登山者が入渓する、ということただひとつ・・・
つづきはこちら
2014年09月03日
ホラの貝ゴルジュ

まるで胎内のようだ。
巨大なホールのように、幾重にもドレープした、滑らかな岩肌が周囲を囲む。その女体を思わせる、エロチックな曲線を霊性を帯びたような青い水が流れる。滝壺は白く泡立ち、轟々と流れゆく。その真っ只中に立ち尽くしていると、気が遠くなり、当初感じた威圧感など消えてしまい、たゆたうような心地よさに包まれる。
ここは、まさに胎内そのものだ、とそのとき感じた
梅雨が明け、二週間ほどは天候が安定することを、山用語で「梅雨明け十日」と言う。まさに週半ばに梅雨明けした週末のこと。思いっきり水と戯れたくて、奥秩父は西沢渓谷の東沢にでかけた。
東沢は下からしっかりと沢筋をたどれば、足も着かない深さ数メートルの釜を持つ滝がいくつもかかる。そのフィナーレにあるのが、碧き清流が流れ渦を巻く、まるで石でできたカテドラル、大聖堂のようなホラの貝ゴルジュだった・・・
つづきはこちら
2014年07月20日
丹沢・モミソ沢と、ヤマビル

【丹沢・モミソ沢遡行~大滝上より右岸尾根下降】
先日。今年の沢初めとして、丹沢のモミソ沢を登ってきた。靴はファイブテン社のキャンプフォーとウォーターテニーを用意した。どちらも生粋のステルスラバーのソールだ。
実は、昨年、ファイブテン社のアプローチシューズ「キャンプフォー」が谷川の万太郎谷などで非常に快適だったので、そのテストも兼ねてのモミソ沢入りだった。
モミソ沢の出合には懸垂岩という、クライミングの初級練習に手ごろな岩場があり、ここは常に山岳会などの初心者練習でにぎわっている。10月頃からは、アイゼンでギャリギャリと音をたてて冬期登攀の訓練に精出す人が多くなる。
さて、このモミソ沢。もう30年以上も前のこと。ボクがまだ16歳だった高校1年の冬に山岳部の仲間と登ったことがある。ルートなんかこれっぽっちも覚えていない。ただ、滝をいくつか越えると水がすぐに消えてしまい、後は普通のクライミングゲレンデを登る感覚で最後の大滝まで行ったこと、そして最後の大滝(12m・Ⅳ級)で怖い思いをしたことだけはしっかりと覚えている・・・
記事全文はこちらへ(CLUB NATURE本館へ)
2013年06月22日
アウトドアと酒

山でお酒を飲んでますか?
お酒があるだけで、アウトドアシーンに心のひだが織り込まれ、情景がお酒の力で醗酵し、実に馥郁(ふくいく)たる香りを手に入れるような気がする。
思い起こせば・・・中学時代の夏休みに歩いた奥秩父の十文字小屋では、汗でシャツをびっしょり濡らした年配のおじさんたちが上機嫌でビールを飲んでいた。「ぷは~うめ~」と大笑いする光景は今でも忘れられない。
この時は荒川源流を訪ねたくて、川又から赤沢出合を経由して歩いた。野鳥鳴き交わすブナの森に響く源流の涼やかな水音にとても幸せな気分だった。稜線まで詰め上がり、甲武信岳をピストンして向かった先は、この日宿泊予定だった十文字小屋。そこの前での出来事だった。
美味そうにビールを飲むおじさんを前に、子ども心に“ビールっておいしそうだな”と感じてしまった・・・
記事全文はこちらへ(CLUB NATURE本館へ)
2012年11月21日
丹沢 大山・北尾根で気軽にバリエーションを楽しむ

マーク・トウェインの小説“トム・ソーヤの冒険”の前書きには「かつて少年少女だった大人たちにも読んでほしい」という著者の言葉がある。
ここに登場するのが、実にわんぱくな少年、トム・ソーヤ。そして彼が大喜びしそうなルートこそが今回の「大山・北尾根」だ。
ここの素晴らしさは数々あって、たとえば、紅葉時期の休日にも関わらず、出会うのはわずかに数組だけとか。またたとえば、明るいブナ林の下、静かで豊かで昔と変わらない丹沢ならではの尾根歩きが存分に楽しめるとか。
大好きな人に「どこか身近な場所で、黄葉の中を気持ちよく山歩きできる場所ないかな」と、ふいにたずねられた際に教えてあげたい、とっておきの場所なのだ。
そもそも、このルートの素晴らしいところは一般的な登山道ではなく、かといって難易度が高く苦労する、なんてこともない。つまり、ある程度の山歩きの基礎経験があれば、地形図と踏み跡をたよりに歩ける、いわば入門的なバリエーションルートといったところ。
この、登山本来のちょっとした冒険気分が味わえ、トム・ソーヤも大喜び間違いなしの素晴らしきルートは、北尾根という名のとおり、大山の山頂から北に伸びている尾根だ・・・
記事全文はこちらへ(CLUB NATURE本館へ)
2012年10月11日
巻機山 登川米子沢の天国に続くナメ滝
新潟・群馬の二県にまたがり、その頂き周辺には、遠い空を星空を映す天界の鏡のような池塘(ちとう)群が静かに広がる。そして、はからずも古より織姫伝説の神秘を抱えた山。
またあるいは、豊富な積雪を持ちながらも奇跡的にスキー場を持たない、いわゆる登山の「聖域」として知られる山。その頂きから谷川連峰や越後三山などのすばらしい展望が思う存分に堪能できる。
この神秘の山こそ巻機山(まきはたやま)だ。
標高は1961メートル。2千メートルには満たないけれど、苗場山や谷川連峰に負けず劣らず、四季それぞれに魅力的な顔を見せてくれる。山頂から南西に延びる井戸尾根の頂きに近い、ちょうど避難小屋の水場付近と山頂直下を水源とするのが今回旅した米子(こめこ)沢。聖域の山にふさわしく、ゴルジュあり、幾多の壁あり、そして天国に続くかのような壮大なナメ滝がフィナーレを飾る、実に素敵な場所。
学生時代にOBに連れて行かれた際には一日中ガスっていた。それが残念で10年ほど前に夏の晴天を狙ってリベンジを果たした。が、いかんせん使い捨てカメラ数枚分のプリントしかなく、年々プリントの色褪せとともに、またその記憶も年を追うごとに薄れてしまった。そして気まぐれに、ときどき思い出しては、ダイナミックな滝に飛沫をあげながらほとばしる水流や、両側から押し迫るゴルジュ、後半のナメ滝にウズウズしていた。
そんな矢先のこと。山仲間から「米子沢行こうよ」との誘いがかかり、天候不良で一度延期した結果、紅葉も楽しめる10月上旬、巻機山へ米子経由の山旅が実現した。
記事全文はこちらへ(CLUB NATURE本館へ)
2011年10月23日
峠ハイキングへの誘い
山に親しんでいると数えきれないほどの“峠”との出会いがある。数えたことはないけれど、山の名よりも峠のほうが多いようにも思えてくる。
ボクが峠に興味を抱いたのは小学4年の頃。登山を趣味としていた母が山仲間とハイキングででかけた十文字峠に連れて行ってもらった時のこと。母の山仲間のひとりが十文字峠についていろいろと話してくれたその中に、十文字峠は昔は中山道の裏道として多くの旅人がた~くさんこの峠を越えて歩いていた、メインストリートだったんだよ、という話がとても衝撃的だった。
目の前には舗装もされていない、歩きにくい山道が山の中に伸びているばかり。これが昔のメインストリートで、たくさんの人が往来していたと想像したとき、ものすごくワクワクした。それ以後、登山と言うより峠歩きがしたくて山の地図を筆頭に「Backpacking」などバックパッキング系の雑誌を読み漁るようになった。つまり当初憧れていたのはクライミングとか登山ではなく、峠を経巡るバックパッキングだった。
しかし高校で山岳部に入部し、大学山岳部、社会人山岳会と流れるうちに峠のことなどいつしか忘れ、どこぞの主稜だの、なんとかフランケとか北西稜だのとクライミングを続けていた。そんなある時、残雪の奥又白のテントの中で会の先輩が「昔の登山家がしたように徳本峠を越えて上高地に入ろうかな」とぼそりとつぶやいた。他のメンバーは今さら峠越えかよ、と笑って終わってしまったが、しかし、この時ボクの中では少年時代の峠を思うときのワクワク感が蘇った・・・
つづきはこちらClubNature+へ
2011年10月03日
日向山で山ランチ

中央線に乗り笹子トンネルを抜けると、青空の下にゆったりとたおやかな峰々を連ねる南アルプスがよく見える。その場所から眺められる北岳、間ノ岳、農鳥岳の白峰三山と呼ばれる山々が昔から大好きだ。
この南アルプスは赤石山脈と呼ばれる。その名の通り「赤い石」が顕著だからそう呼ばれ、それは沢登りで赤石沢などに入れば清流に磨かれた赤い石がとても美しいことからもよくわかる。赤石沢に最後に入ったのはすでに10年も前だから、とても懐かしい。
火山性の北アルプスなどとは生い立ちを全く異にする南アルプスは、フォッサマグナによる地殻隆起によっているため甲斐駒の一部をのぞいて水成岩からできている。その甲斐駒ケ岳や鳳凰三山は花崗岩からできていて地蔵ヶ岳のオベリスクなどの白い山稜部は桃源郷の甲府盆地からでもよく見える。
地殻隆起でできあがっているので森林限界がとても高く、北アルプスの2500メートルに比べ、南アルプスでは2700メートルにまで上昇する。そのために樹木に覆われた濃厚な印象があるのだろう。
さて、この南アルプスの中で、週末ランチを楽しみに家族あるいはひとりでフラリと出かける場所がある。それが八ヶ岳の格好のビューポイントでもある日向山(1659メートル)だ。
つづきはこちらClubNature+へ
2011年09月12日
夏は沢登りで僕らはトムソーヤになる

「あなたは、最近“冒険”をしていますか」
そんな質問をされたら頭を捻ってしまうだろう。それは、きっと、僕らが大人になってしまったからなのかもしれない。
思い起こせば少年時代。手足に生傷を作りながら藪に飛び込み、ドブ川横の野原を探検し、それでも飽きたらずに小さな庭の木の茂みの影や、あるいは家の中の納戸だって。想像力たくましいわんぱく少年にとっては、なんでもかんでも“冒険”の対象になったし、未知の体験との遭遇がそこにはあった。
“冒険”という言葉にワクワクしてしまう大人はきっと多いに違いない。今の子供たちのことは知らないけれど、ちょうど僕らの世代であればマーク・トウェインの「トムソーヤの冒険」とか映画の「スタンド・バイ・ミー」などを知っているのではないだろうか。で、もちろんBGMは“When the night has come. And the land is dark~~~”で始まるベン・E・キングの「スタンド・バイ・ミー 」です。
つづきはこちらClubNature+へ
2010年09月27日
八幡平 ネイチャートレイル
八幡平NATURE TRAIL
東北の代表的なアスピーテ(楯状火山)帯が八幡平。そこには、アスピーテ特有の広々とした大地に隆起したピーク周辺に実に美しい湿原が数多く点在する。出かけたのは9月24日。
アウトドア雑誌で頻繁に取り上げられるバックパッキングルートに、ジョンミューア・トレイルなるものがある。しかし、それらアウトドア系スタイルマガジンで取り上げられる場所に負けない多くのトレイルが日本には存在する。そのひとつが「ジョン・ミューアトレイルよりも北アルプス・トレイル」というような過去記事にした北アルプスのルートだったりする。
もちろん雁ヶ腹摺山周辺や奥秩父エリア、はたまた南アルプスエリアやら奥日光そして奥羽山脈擁する東北方面にだって素晴らしい数々のトレイルがある。それらをゆっくりと味わうようにして巡り歩けば、それだけで人生がふくよかな豊穣に満たされるに違いない。
アルパインクライミングにどっぷりとのめり込んでいた時期もあったけれど、どうもこの頃ではこうした遥かな雲上の道を、風景を肴に歩いて楽しむ悦楽に心動かされて仕方ない。
この“雲上トレイル”で好きなもののひとつが稜線に広がる高層湿原だ
つづきはこちらClubNature+へ
2010年09月21日
奥飛騨 高原川・沢上谷
今年、2010年のゴールデンウィークは雪の前穂北尾根~奥穂~西穂を周遊し、途中で槍に向かうという仲間と別れて西穂ロープウェイで降りた下界で、数年来Blogで交流をさせていただいてきた山仲間との邂逅をとうとう果たすことができた。「その男藪漕ぎ中」というBlogを主宰している“いまるぷ”さんだった。
※メンバーのブログリンクは最下段
できれば、夏が終わる前に、どこか気持ちのいい場所をたわいもない話に笑いながら歩きたい。
猛暑厳しい今年の夏。涼しく快適に、静かに楽しくそれでいてハイキングとは違った山らしいワクワク感が楽しめるプチ山旅・・・ということでチョイスしたのが奥飛騨の高原川・沢上谷(そうれだに)。乗鞍岳を源流とし奥飛騨温泉郷平湯、そして平家の末裔と言われる福地の集落を抜けて栃尾で蒲田川と合流する清流に、神岡の西で注ぐ美しき支流だ。
時期は・・・夏がフィナーレを迎える前の、焼くような陽射しに一抹の寂しさが交じる9月初旬。5人の素敵なアウトドア仲間と夏のかけらを味わいながら、他愛もない話に笑いながら、しみじみと数時間ばかりの山旅を楽しむという企画が実現した...
つづきはこちらClubNature+へ
2010年07月20日
奥多摩・川乗谷逆川 2010沢初め
さあやってきました、サワノボラーの季節です。
“沢登りなんてものは冬になればアイスクライミングと名を変えて、凍った滝をダブルアックスで登って愉しめるし、通年楽しめるじゃん”と言われてしまえばそれまでなんですけれど。
でもね・・・ジリジリと肌を焼くような日差の季節に、ヒャッコイ・チベタイ沢水の中をシャワシャワと歩き、滝つぼを泳ぎ、飛沫をあげる滝のその水流中を登って愉しむ沢登りは・・・やっぱり夏こそオンシーズン。夏の最高のアウトドアのアクティビティです。
奥秩父のナメ系か、奥多摩で泳ぎ主体の丹波川本流やら面白い滝がてんこ盛りの海沢谷、はたまた“モリノ窪瀑流帯”などというなんだか恐ろしげな名のゴルジュ帯を持つ小川谷・犬麦谷のどれに行こうか・・・と考え、最終的にアプローチの容易さと、ツメの藪漕ぎが無く、ウスバ乗っ越しから入渓地点の南西方向へ尾根を落とすウスバ尾根で下山できるというポイントを重視して選んだのが奥多摩の川乗谷逆川。パートナーは仕事仲間であり、山&カヌー&キャンプ仲間でもあるjin_bravo氏・・・
つづきはこちらClubNature+へ
2010年01月09日
雪とアウトドア
先日、幕張のカフェでのこと。
打ち合わせが終わり、海を眼前いっぱいに眺められるレストランで仕事仲間と食事をした。その際に、次回のスノーハイクのことを彼に話し「やっぱり雪はいいよなぁ」と呟いたボクに「ここは雪国じゃないからだよ」と、その知人がぼそりと言った。
聞けば彼の故郷は山形で、朝起きれば玄関前の雪かき、屋根の雪下ろしにはじまり、四六時中雪と格闘していると話してくれた。屋根の雪下ろしをしないと重みで玄関も開かなくなるのだとか。暗くどんよりした日々が続き、そこで生活していると「雪を見たくなくなる気持ちにも時としてなるんですよ」と彼。
そういえば江戸時代の文人、越後の鈴木牧之(すずきぼくし)翁も、その著書・北越雪譜で「江戸人は雪を粋なものとして愛でるが、それは雪国に生きぬ者たちだからだ」というようなことを記していたことを思い出した。何事も過ぎたるは及ばざるが如しものということか。ボクが移り住んだこの外房には全く雪が降らない。まさに、雪に関しては「及ばざる」エリアだけに、雪への憧憬もより大きくなってしまうようだ。
つづきはこちらClubNature+へ
2009年12月28日
スノーペグを作る楽しみ

木枯らし吹いて、初冠雪が穂高や富士の頂きをうっすら染める頃になると、決まってすることがあります。それがスノーペグ作りです。材料の竹は、以前はホームセンターから数百円ほどで調達していましたが、現在はすぐ横の竹やぶからもらってきます。
この竹をナタで4つ割りの竹板にして、それを15センチから20センチ程度の短冊に切って真ん中に穴を穿ち麻ひもを通して完成。天気の良い休日など新聞紙を広げた上でこの竹板の周囲を小刀でカリカリと削っていると、あぁ冬だなぁ・・・と思うわけです。これは、もう高校時代から変わらぬ、冬を迎える儀式のようなものです。
つづきはこちらClubNature+へ
2009年12月07日
素晴らしきクライミング

写真はBlog「放置民が行く」の“いのうえ氏”が撮影
歳をとっても楽しめる素晴らしき趣味のひとつがクライミングだ。
しかし、どうも“クライミング”と聞くと、若いときにしかできないもの、という考えを持つ方も多く、昔いっしょに登っていた仲間の「いつまでもクライミングなんかやってられないしさ」とか「子供がいるんだぜ。死にたくないよ」などという言葉を聞くたびに心中で舌打ちしたくなってしまうのだ。
ボクは、学生時代のようなクライミングではなく、困難さとは無縁の気持ちのいいアルパインルートを楽しもうとしている、のにだ。
山をより深く楽しみつくすには、やはり、登山道を歩く“山歩き”だけでなく、手足と頭脳を駆使して登る“山登り”だと思う。そして“山登り(クライミング)”とは言っても、なにも難易度の高いルートばかりがあるわけではない。
たとえば難易度の高いアルパインルートを攻略するクライマーが存在するいっぽうで、クラシックなアルパインルートを楽しむクライマーも多い。後者には、学生時代に山岳部で登っていた方や山岳会で技術維持・レベルアップをしている方はもちろん、講習会に参加して技術習得に励む方など、それぞれが自分にあった方法で技術を学び、レベルに見合ったルートで山を思う存分楽しんでいる。
未踏峰を狙ったり、いまだ困難さゆえ攻略されていないルートを攻めるようなことは目的としていない。だからといってあまりにも簡単すぎるルートは面白くない。多少、難易度が高く、クライミングにともなうアドレナリンによる高揚感が味わいたいのだ
つづきはこちらClubNature+へ
2009年11月21日
雪山・スノーハイクと鹿澤館

雪山には一種独特の特有な匂いがある。
あちこちの山が冠雪する今の時期になると、鼻腔の奥にかすかにツン・・・と雪山の匂いがして、憧れのひとと初めてデートする直前のような、そんなそわそわとした落ち着かない気分になる。
一日しか休みがとれず、どうにも身動きが取れない週末など、もう無意識のうちに身体が反応し、納戸からガチャガチャとクランポンやピッケル、スノーアンカーだのを無闇やたらに引っ張り出しては撫で回したり、すでにギンギンに研いであるクランポンの歯に鉄ヤスリをカタチだけ当ててみたり。そうしていることで、少しでも雪山に近づいたような気がして落ち着くことができるから不思議だ。
さて、出かける場所は様々で、山仲間とは大好きな白馬の主稜を筆頭に、奥穂や谷川あたりに向かう。しかしいっぽうで、のんびりと雪と戯れに磐梯あるいは鹿沢高原、霧ヶ峰・蓼科、北八ッなどにフラリと向かうことも多い。中でもひと冬に何度か訪れるエリアが奥蓼科・霧ヶ峰と鹿沢高原・湯の丸山周辺で、特に鹿沢高原で雪中野宿しながらスノーハイク(または山スキー)していると、吹雪の晩などまるで戦前の登山黎明期にタイムスリップしてしまったような、妙な気分に浸ることができる。
おそらくそれは、鹿沢高原にある「雪山賛歌の碑」のせいだろうと想像している。
つづきはこちらClubNature+へ
2009年10月28日
白馬の道祖神が集う場所
道祖神といえば、思い浮かぶのは男女ふたりが仲睦まじく寄り添うようなその姿。
それを見ていると、なんだか自然と笑みがこぼれてしまいそうになる。こういう笑みがこぼれるのを面足(おもだる)と言うらしく、神社の良縁の御守りに面足大神と記されるのを見ることもある。
良縁すなわち男女の出会い。そこから生まれる笑顔や喜びは豊穣にもつながるようで、陽陰すなわち男女の象徴はそのまま豊かさを願って作られたモニュメントなどに見て取れる。
こうした男女の印象が強い道祖神には巡り歩いてみれば単独のものも意外と多い。それらが建てられる場所は集落の境の道や辻が多い。道とはそもそも外界と通じる霊的なもので、新たに道を切り拓くのに、霊的な呪として人の首を携え悪霊を祓って行われた。それゆえに道という字は首を携え進むことが表現されている。
塞(さえ)の神・猿田彦の印象なども、なんとなく重なるようでもある。
さて、外界との間境に置かれた道祖神は、もしや男女の出会いの場としての機能を備えていたのではないのか
つづきはこちらClubNature+へ
2009年10月26日
木賊温泉で男っぷりを磨く
混浴から出てきた若いご夫婦
世の中に秘湯と呼ばれる温泉は有料無料ふくめて数多い。その星の数ほどある中の、これぞ温泉の原型か、とも思うのが木賊温泉。木賊(もくぞく)と書いて「とくさ」と読む。
「とくさ」は「砥草」。細い棒状の形状で、草の表面にケイ酸が硬化したものがあり、指でなぞるとまるで細かな紙やすりのような感触があり、この茎で砥ぎを行うことができるので「砥草」。かつての木地師などは砥草で木を磨いていたし、意外なところでは滝廉太郎をはじめ、多くの古きオシャレな方々は砥草で爪を艶やかに磨きあげていた。
この砥草の仲間にスギナという草がある。ボクはスギナを山ほど採取し乾燥させたのを煎じて飲んでいる。このスギナの効能がまた素晴らしく、悪き物を対外に出してしまうらしい。なんでも子宮筋腫なども流し出してしまうと聞いたことがある。免疫力を高めるのだったか、とにかく以前身体が不調の際に薬草の本を調べスギナを飲み始めすっかり改善されてしまった。
これらは古くは「もくぞく(木賊)」と呼ばれた薬だったため、木地師の「とくさ」の呼び名が漢字に当てられ、それで木賊と書いて「とくさ」と呼ばれるに至ったのだと思う。
さて、こうした漢方の名が付いた木賊温泉は、その名の通り素晴らしく疲れた身体を癒してくれる。
つづきはこちらClubNature+へ
2009年08月27日
ゴジラの背
山好きな方に“ゴジラの背”と言えば、これはもうほとんどの方は「北穂東稜」を想像することでしょう。涸沢から北穂に至るルートである南稜をエッサエッサ登っていると、向こう正面に見える急峻な岩尾根が東稜、通称「ゴジラの背」。ギザギザしたシルエットがゴジラの背のように見える岩尾根です。キレットよりもややショッパイですが、快適にクライミングしつつ北穂に突き上げる気分ヨシのバリエーション。
さて、このゴジラの背は何も穂高ばかりではなく、なんと房総・館山にもあったのだからオドロキ・モノノキ・サンショノキ。上の画像がそれで、北穂東稜よりも丸みを帯びていて、この有機的さ加減がめちゃくちゃゴジラの背っぽいではないか
つづきはこちらClubNature+へ