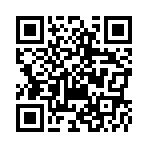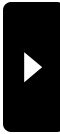2009年03月26日
田舎暮らしの貧格 なるようになるさケセラセラの巻
近くの里山の森にて:田舎暮らし自由人の貧格度ある小屋
田舎暮らしの貧格・その三
田舎暮らしを始めて次第に貧格(ひんかく)力がアップすると、あらゆる事物を受け入れることができるようになるため、ちょっとやそっとのことには動じなくなる。
たとえば・・・「なるようにならぁね」「えーい、ままよ」なんて、こうした言葉を生み出したのは、日本の近世において最も貧格度が高かったと思われる長屋住まいの江戸っ子たち。
これをイスラム的に言えば「インシャラー」、神の思し召しのままに・・・となるのだろうか。同じくアラブ系のラテン諸国であるスペインやフランスにも、なるようになるというような意味の「ケセラセラ(Que sera,sera)」なる言葉がある。かの国々は中東と血がつながっているラテンの国だけに、これの根っこも「インシャラー」なのかもしれない。
貧しくとも悩まず底抜けに明るい。物至上といった呪縛から開放された、ある種、達観したような境地こそが“田舎暮らしの貧格”の到達点とも言えそうだ。
身持ちの金銭は減るけれど、人間としての品度は落とさない。いや、逆に品度を上げねば貧には勝てない。懐が貧となり人間も貧と成り果ててしまえば、元も子もないし、わざわざ豊かな生活を捨てて田舎に移住した意味がない。
さて、貧格度をあげるために一役買うのが、現金の放出を余儀なくされる数々の機会。自治会費にはじまり宅配便による通販の代引きお届け、赤い羽根募金やら地域の冠婚葬祭の集金などなど。
本館はこちらClubNature+へ
Posted by ユウ_zetterlund at 10:48│Comments(0)
│country life
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。